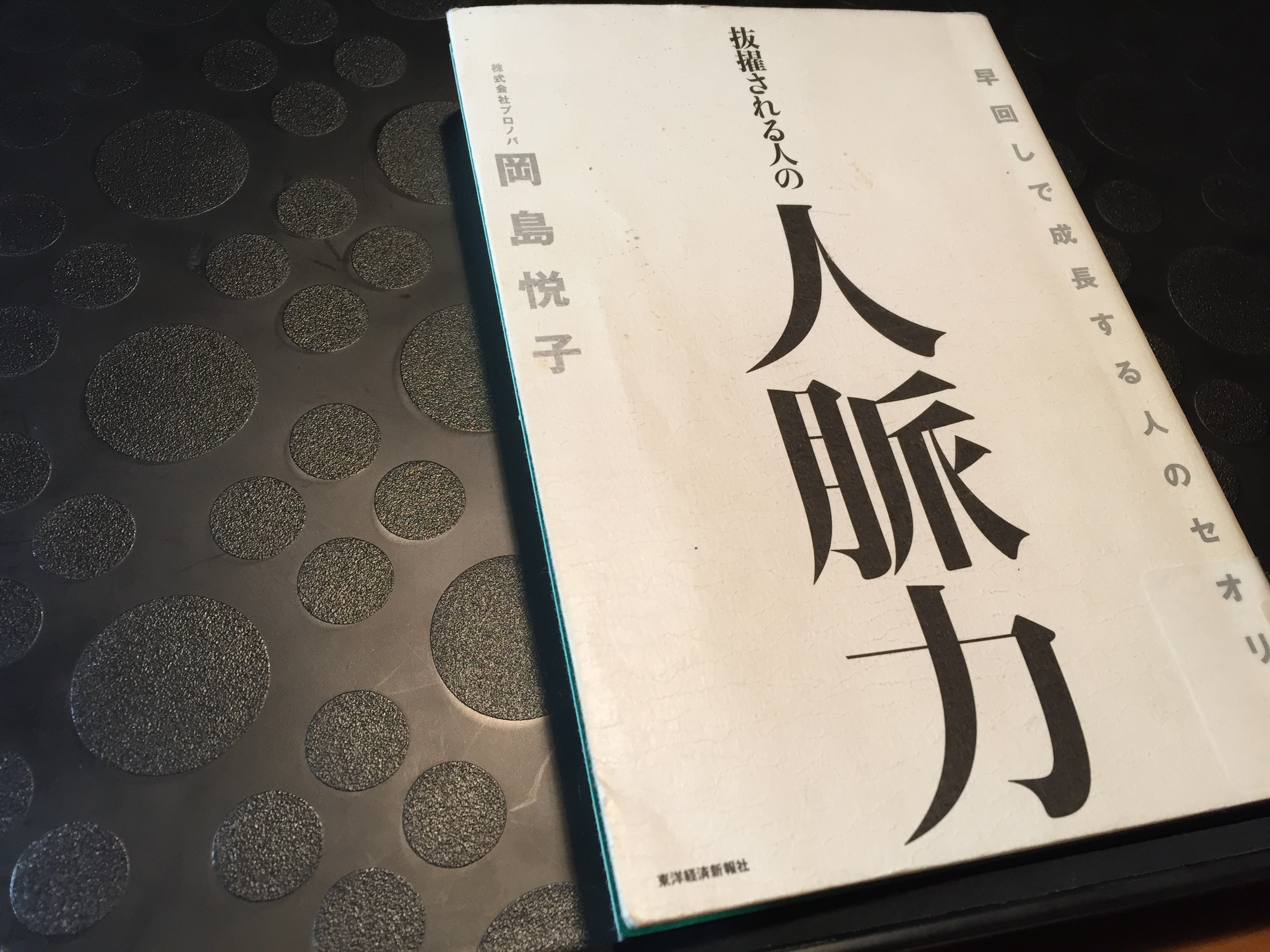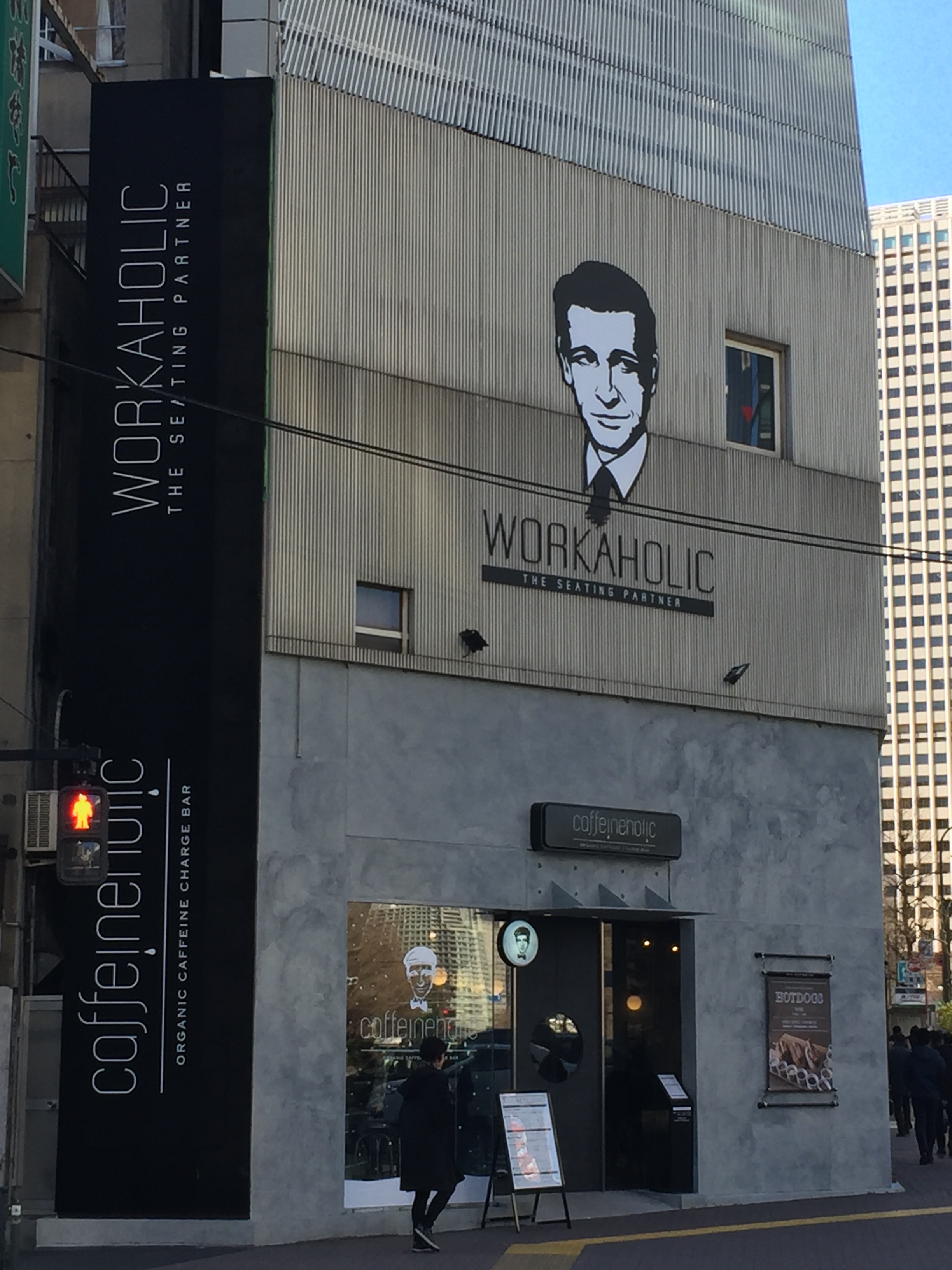【書評】井上 昌次郎 著『ヒトはなぜ眠るのか』
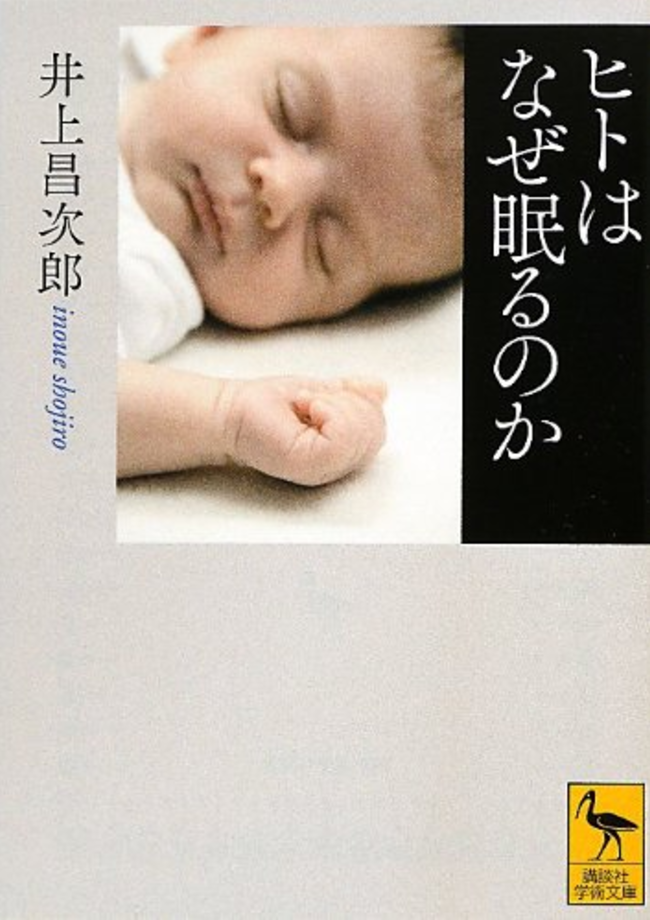
著者は、脳科学・睡眠学が専門の大学教授。
本書以外にも、睡眠に関する本を多数執筆されています。
冒頭は、タイトル通り、人はなぜ眠るのかというテーマで始まります。
睡眠本は、ほとんどテーマが決まっていますね(笑)
冒頭では、この答えが示されず、「この本のなかでわかりやすく示したい」と書かれています。
レム睡眠とノンレム睡眠
そして、本書もまずはレム睡眠とノンレム睡眠の説明に移ります。
ノンレム睡眠は、浅い状態と深い状態に分けられますが、
著者は脳が眠る深いノンレム睡眠を”ぐっすり眠る睡眠”、身体が眠るレム睡眠を”ぐったり眠る睡眠”と表現しています。
面白い表現ですね。
また、ノンレム睡眠を”眠る脳”、レム睡眠を”眠らせる脳”とも表現しています。
そして、ノンレム睡眠とレム睡眠は90分単位で構成されていますが、寝入りばなの最初の2単位である3時間のあいだは、深いノンレム睡眠がまとめて出現するとのこと。
以後は、浅いノンレム睡眠とレム睡眠の組み合わせだそう。
つまり、以後はいわばおまけの浅い眠りだと言っています。
本書では、これについて、何度か全く同じことを書かれています。
長時間眠ることはその分、質の悪い浅い眠りが現れるので起きた時の気分は悪く、身体はぐったりして、かえって疲れてしまうので、多すぎる眠りはむしろ害があると言っています。
と言っても、著者は短眠を推奨しているわけでは全くなく、著者自身は、睡眠時間を振り替えて何かをするよりも、逆に何か仕事を削り、ゆっくりごろ寝して幻想を楽しむ方を選びたいと書かれています(笑)
本書でも、鳥類や哺乳類のように大脳が大きく発達するに従い、レム睡眠のままでは欠陥技術になり、新たにノンレム睡眠という技術が開発され、レム睡眠も捨てられることなく生き残ったことから、2種類の睡眠があると書かれています。
長時間睡眠者と短時間睡眠者
そして、睡眠について書かれた本にはよく、過去の偉人の長時間睡眠者と短時間睡眠者の例が書かれていますが、本書でも同様に触れられています。
長眠者として有名なのは、アインシュタインで、毎日10時間睡眠。
短眠者としては、ナポレオンとエジソンで、3〜4時間程度。
多くの本に記載されている例です。
そして、面白いのは、これもよく書かれていますが、レオナルド・ダ・ヴィンチの例。
この天才は、4時間ごとに15分寝ていたと言います。
合計して、1日に90分。
本当だったとしたら、これまでに解明されている睡眠についての研究結果でいう、大脳を休めるためのノンレム睡眠が取れていないのでは? という疑問が湧いてきます。
天才は、脳の構造が違っていたということなんでしょうか?
一方では、アインシュタインのように長眠者のほうが、自由な発想のできる創造性豊かな人だという説が提唱されたりもします。
本書では、他にも何人かの睡眠事例が紹介されていますが、著者は多くを説明せず、睡眠は人それぞれで、多様性に富むものだと結論付けしています。
僕は同じ種類の生物に、それだけの個体差があるとはとうてい思えないですが、どうなんでしょう?
本書では、いろんな動物の睡眠についても掲載(レイ・メディス著『睡眠革命』からの引用)されています。
一番睡眠時間が長い動物は、オオナマケモノで1日20時間、逆に短い動物は、ウマなどで2時間となっています。
レイ・メディス著『睡眠革命』からは、短眠の人の事例も掲載されていて、1日平均1時間未満とか10分未満という人までいるようです。
このように極端な短眠でありながら健康に長生きしている人がいるわけですが、著者はこのような人たちもまったく睡眠なしに生活しているわけではなくて、何らかの方式では睡眠機能が補填されていると言っています。ただ、これまでの睡眠の常識が通用しないわけです。
効果が高い睡眠
レオナルド・ダ・ヴィンチのように、1日に何回も眠るパターンを「複眠」あるいは「多相性睡眠」、1日に1回まとめて眠るパターンを「単眠」あるいは「単相性睡眠」といいますが、今の時代、ほとんどの人が1日に1回まとめて眠っていますよね。
でも、もともと人の睡眠は多相性だそうです。
そこで、一つ面白い実験が紹介されています。
寝床にいる時間を1日8時間と決めておき、半分の4時間を夜間にまとめて眠ります。
そして、残りの4時間をどのように配分するかで、作業能力や頭脳活動の結果を検証した実験です。
総合成績が一番良かったのは、副睡眠を20分ずつ12回に分けて取る方法だったとのこと。
熟睡に相当する深いノンレム睡眠は短い副睡眠では出現せず、目覚めが良いうえに、身体諸機能の回復が早く、主睡眠で熟睡できるので睡眠不足になりにくいようです。
なかなかこんな生活はできませんが、よく言われるように昼寝やパワーナップを取ることが良いというのは正しいみたいですね。
まとめ
本書の著者は、睡眠に関する著者の多くが展開しているような「ある程度の睡眠は絶対に必要」というな主張をしておらず、人の睡眠は個人差が大きいものであり、また融通が利くものだと言っています。
様々な条件に柔軟に対処できる多様性を備えていて、工夫次第で好ましいものに向上させ、生活の質をより豊かに充実させることができるといいます。逆に、睡眠を犠牲にしたり軽視したりすべきでもないと言っていますが、要は「1人ひとりが責任を持って自由にしましょう」ということですよね。
とりあえず、今わかっていることだけを記載しており、持論はそれほど展開していません。いろいろと書いてくれていて、睡眠について知りたい人にはオススメです。
ちなみにタイトルの『ヒトはなぜ眠るのか』。
本書で示す答えは、「もともと生物にある身体を休めるレム睡眠と、高等動物であるヒトは発達した大脳を休めるためのノンレム睡眠の2種類が必要だから」
でしょうか。
僕は、次は本書で引用されていたレイ・メディス著『睡眠革命』を読んでみようと思います。
どうぶつ社
売り上げランキング: 884,467